はじめに
「品質第一」という言葉は製造業の現場でよく聞かれます。確かに、製品の安全性や信頼性を確保することは最重要課題のひとつです。
しかし、“品質さえ良ければ原価が高くてもよい”という考えが設計段階に残っていると、コスト競争力のない製品が生まれてしまいます。
この記事では、設計初期から品質(Q)と同時にコスト(C)を意識すべき理由を、実務的な視点で解説します。
設計初期=コスト構造が決まるフェーズ
設計初期とは、製品の仕様や構造がまだ自由に決められる段階です。 この段階で決める内容が、製品の原価に直結します:
• 材質の選定(ステンレス or 樹脂)
• 構造の複雑さ(部品点数・組立難度)
• 精度や表面仕上げの要求
これらはすべて、後工程では変更が困難になる“コストの固定要因”です。
なぜQだけに偏るのか?
• クレームや品質事故への恐れ → 安全マージンを広く取る傾向
• 評価基準がQ主軸(強度、安全性、規格準拠)
• コストは設計者の“見えない責任”になりがち
結果として、「過剰品質」が設計に潜むことになります。
コスト(C)も初期で検討すべき3つの理由
- 後からでは変更できない
o 試作後や量産開始後では構造変更=大規模な設計変更となり、困難 - 設計の選択がそのまま価格に跳ね返る
o 部品点数、材質、構成はコストの根源 - 顧客が求めるのは“バランスの良い製品”
o 高品質=高価格では市場競争に負ける可能性も
実例:筐体カバーの材質選定
• 設計者判断で「傷つきにくく、硬い」ステンレスを採用
• 実際の使用環境では、ABS樹脂で十分耐久性があり、軽量かつ安価
• VE会議で材質見直し → 材料コスト40%削減、組立工数も半減
→ 品質を維持しながら、コストに大きな効果をもたらす結果に
まとめ
設計における品質(Q)とコスト(C)は“対立”ではなく“両立”が可能です。
そのためには、設計初期からコストを「制約条件」ではなく「設計要件」として組み込む視点が必要です。
“この設計は品質を満たしているか?”と同時に、“この構造は最適コストか?”という問いを常に持つこと。 それが設計原価低減の第一歩です。










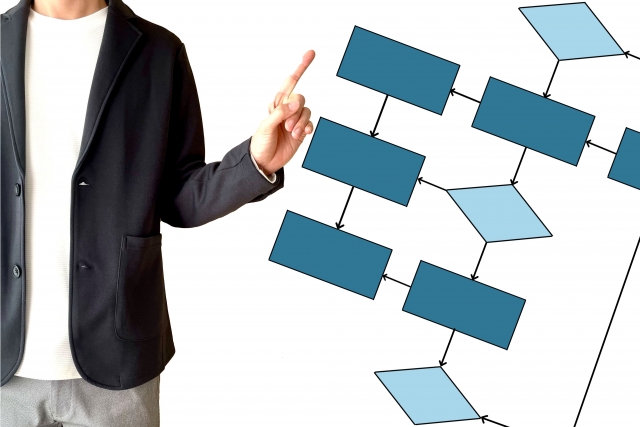



コメント