はじめに
「海外の方が安い」は、本当に正しいでしょうか?
調達単価だけで判断すると、海外調達が有利に見えるかもしれません。しかし、実際には為替リスク・輸送費・関税・品質・納期トラブルなど“見えないコスト”が多く、**TCO(Total Cost of Ownership:総保有コスト)**で比較することが重要です。
本記事では、グローバル調達を判断するためのフレームとコスト要因の見える化手法を紹介します。
国内調達と海外調達の主なコスト要因
| 項目 | 国内調達 | 海外調達 |
| 調達単価 | △ | ○(一見安い) |
| 輸送費 | ○(低い) | △(国際輸送+保険) |
| 関税・通関費 | ○(不要) | △(発生・変動) |
| 為替リスク | ○ | △(円安でコスト上昇) |
| リードタイム | ○(短い) | △(長く、不確実) |
| 品質・歩留まり | ○(安定) | △(国によって差) |
| コミュニケーション | ○(容易) | △(言語・文化差) |
TCOで見るべきコスト全体像
- 輸送コスト(国際運賃、保険、倉庫料)
- 税金・関税(HSコードの取り扱いに注意)
- 為替差損リスク(長期契約ではヘッジを考慮)
- 品質コスト(不良対応・再発注・検品)
- 在庫コスト(リードタイムが長く、余剰が発生)
- 管理工数(監査・現地視察・トラブル対応)
これらを見える化・数値化し、単価ではなく総コストベースで国内と海外を比較することが合理的判断に繋がります。
実例:海外調達が逆転したケース(あくまでも参考値)
- 電子部品の海外調達で単価は30%安かったが、輸送費と不良対応のコスト増で実質は5%増
- 国内サプライヤーにVE提案を依頼 → 単価15%減+リードタイム短縮に成功
まとめ
価格だけでは判断できないのがグローバル調達。 TCOの視点で“本当に得か?”を比較するフレームを導入することで、調達戦略はより安定し、持続可能なコスト改善に繋がります。









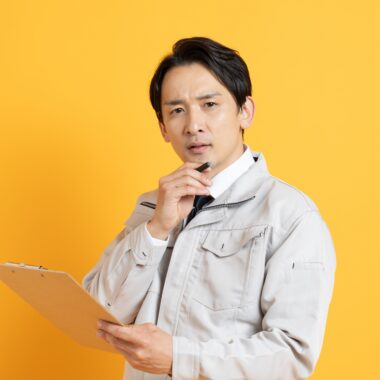






コメント