はじめに
VE(Value Engineering)は、機能本位の発想で不要なコストを排除し、価値を最大化する手法です。実務でVEを実践するには、ステップごとの流れを具体的に理解することが重要です。 この記事では、架空製品「商品A」を用いて、VEの各ステップを追体験できるように実例形式で紹介します。
ステップ1:情報収集
商品Aの構成部品・機能・コスト構成を明確化。材料費、加工費、外注費などを部品単位で洗い出します。
ステップ2:機能定義
各部品の目的を「基本機能/二次機能」といった分類で定義。例:アルミカバー→「「強度を確保する」「放熱を放つ」「放熱をする」
ステップ3:機能評価
定義した機能ごとにコストを配分し、「高コストだが重要性が低い機能」を特定。
ステップ4:代替案の発想
特定した機能「強度を確保する」「放熱を放つ」
- アルミ→樹脂素材へ変更+放熱スリット追加
ステップ5:評価と選定
代替案の実施前試算で、コスト20%削減、性能維持
まとめ
ステップを順に踏むことで、VEは再現性のある改善手法となります。商品Aの例はあくまで一部ですが、あらゆる製品に応用可能です。
大きな流れとしては抜本的な改善を行いたい場合はアッセンブリより行い、小改善の
場合は図面に対するアプローチが有効です。
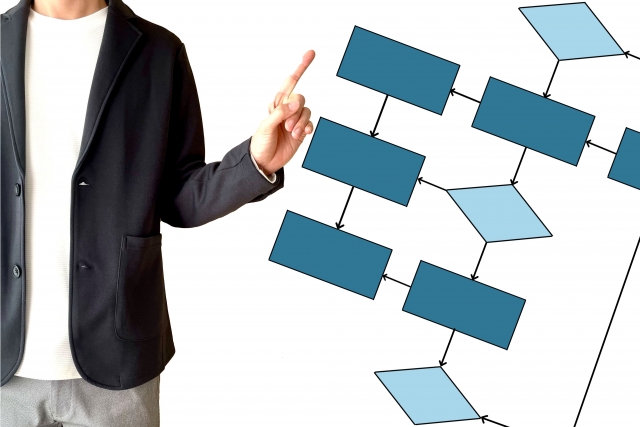













コメント