はじめに
企業が利益を生み出すうえで避けて通れないのが「原価」の管理です。
特に製造業では、製品が売れた後の利益は「売上 - 原価」で決まり、原価の構造を正しく理解していないままコスト削減に走ると、逆効果になることもあります。
この記事では、
• 原価とは何か?
• 製造原価、販売原価、総原価の違い
• 原価を構造的に見るとはどういうことか?
についてわかりやすく解説します。
1. 原価とは?
原価とは、製品やサービスを提供するために企業が費やした費用のことです。
主に以下に分類されます:
• 製造原価:材料費、人件費、外注費など「製造に直接関わる費用」
• 販売管理費(販管費):営業・管理部門の人件費や広告費など
• 総原価:上記2つを合わせた「会社全体でかかるコスト」
※よくある誤解:「原価 = 仕入値」ではありません。原価とはもっと広い概念です。
2. 製造原価の内訳
製造原価はさらに細かく分類されます。
• 直接材料費:製品に使う鉄板、樹脂、部品など
• 直接労務費:組立工の作業時間・人件費
• 製造間接費:工場の電気代、保守費、間接人件費など
これらを可視化することで、「何にコストがかかっているか」が把握できます。
3. 販売管理費(販管費)とは?
製造以外に発生する、営業活動や管理部門のコストです。
• 営業人件費
• 広告・販促費
• 事務・総務・経理などの間接部門の人件費
販管費は削減しやすく見えますが、戦略的判断が必要です。
4. 総原価とは?企業活動全体で見るべき視点
総原価(全部原価)= 製造原価 + 販売管理費
損益計算書の中では以下のように構成されます:
• 売上高
• - 売上原価(≒製造原価)
• = 売上総利益
• - 販管費
• = 営業利益
製造現場だけでなく、間接部門のコストも含めて全体を見る必要があります。
5. 原価を構造的にとらえる視点
「どこに、どれだけ、どの工程でコストがかかっているのか?」を可視化することが原価管理の第一歩です。
例:製品Aの原価構成比
• 材料費:45%
• 加工費:25%
• 間接費:20%
• 販管費:10%
この構成から、材料費・加工費・販管費などどこに手を入れるかを判断します。
まとめ
• 原価とは「製造原価」と「販管費」の集合体である
• 原価低減を行うには、まず構成を分解・見える化することが重要
• 「VE」や「設計改善」「調達改善」などの具体策は、原価構造の理解があってこそ意味を持つ















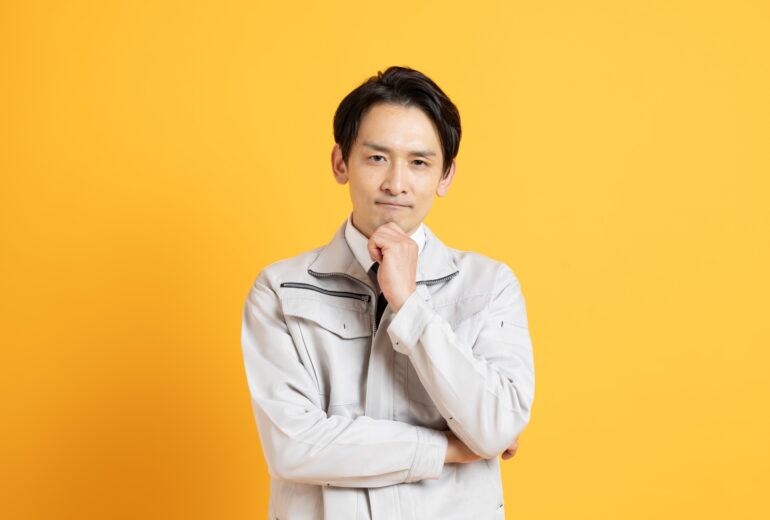
コメント