原材料価格の高騰や競合の激化など、製造業を取り巻く環境は日に日に厳しくなっています。
そんな中、コストダウンと品質維持を同時に実現するために注目されている手法が「VA(Value Analysis)提案」です。製品の機能を最適化しながら余分なコストを削減するこのアプローチは、各種業界で導入が進んでいます。
しかし、正しい進め方を知らないまま進めると、期待した効果が得られなかったり、現場との連携がうまくいかずにストップしてしまうリスクもあります。
本記事では、VE提案との違いや実際の取り組み例、さらには成功事例や具体的な進め方を解説します。歴史的な背景も踏まえ、どのように自社で活かすかヒントを得ていただけるようまとめました。
VA提案とは
VA(Value Analysis)提案とは、製品・部品などに含まれる要素のうち、必要とされる機能を保ちながらコスト削減や生産性向上を図る手法です。
具体的には、材料・設計・製造工程などを分析し、どこに改善の余地があるかを見極めたうえで、新しいデザインや加工方法、材質変更などの具体案を提示します。
VE提案との違い
似た概念として「VE(Value Engineering)」があります。VEとVAは同じ「価値を高める」という考え方をもつ手法ですが、以下の点で主に区別されることが多いです。
- ・VE:新規設計段階でコスト削減と価値向上を狙う(開発・設計フェーズ)
- ・VA:既存製品や既存工程を分析・改善し、コスト削減と機能向上を狙う(改良フェーズ)
VEはプロダクトの立ち上げ期に適用され、VAは量産や市販後の既存製品のコストダウンに活用されるイメージです。ただし、企業によってはVEとVAをほぼ同義として扱うこともあります。
VA提案の取り組み例
製造業でのVA提案は、業界や製品の特性によって実施内容が大きく異なります。ここでは、自動車製造業界と建設業の工事現場におけるVA提案の例を紹介します。
自動車製造業界
自動車の車体やエンジン、内装部品など、多彩な部品から構成されるため、VA提案の対象が多いのが特徴です。
- ・素材変更:鋼板を高張力鋼やアルミ合金に変えて軽量化し、燃費改善とコストダウンを両立
- ・形状変更:バンパーやドアの構造を簡易化し、金型費と組立工数の削減を目指す
- ・部品統合:複数の部品を一体成形にすることでネジなどの締結部品を減らし、在庫や工程をカット
こうした改良は、安全性や強度といった機能を満たしながら、材料費や労務費の低減を可能にします。
建設業の工事現場
建設現場では、建材や施工方法などを工夫してコストと工期を抑えながら、建物の機能・耐久性を維持または向上させる取り組みがVA提案の中心です。
- ・コンクリート配合を最適化:必要な強度を維持しつつ高価な添加剤を減らす、骨材の選定を見直すなど
- ・構造材の統一:梁や柱の寸法・形状を標準化し、製造・配送コストや施工手間を削減
- ・施工工程の見直し:プレファブ工法やユニット化による組立て短縮で、人件費や納期を短縮
VA提案の成功事例
ここでは、実際にVA提案で成功を収めた事例を3つ取り上げます。
企業の業種や製品形態が異なっても、共通するプロセスがあるため、自社の状況と照らし合わせながらヒントを探すことができます。
材質の変更によって納期短縮を実現
ある家電部品メーカーでは、金属部品の材質をステンレスから特殊樹脂に変更するというVA提案を行い、加工工程を省略することに成功しました。その結果、加工工程の削減によりリードタイムが約20%短縮され、納期へのレスポンスが向上しました。実施にあたっては、樹脂でも必要な強度を満たすかどうかを事前にテストし、品質保証部門と十分に協議したうえで進められました。
組立図面を工夫し部品の精度を向上
建機部品の組立工程では、組立手順が複雑になっていたため、不良品ややり直し作業が発生していました。そこで、図面をVAの観点から整理し、各パーツの取付けガイドを追加するなどの改良を行いました。その結果、組立ミスや部品の破損が大幅に減少し、品質不良や再作業にかかるコストを大きく低減することができました。改善にあたっては、現場作業者へのヒアリングを通じて、どこでエラーが起きやすいのかを把握し、的確な対策を講じました。
加工方法を改善しコストを削減
金属加工において複数の工程を経ていた製品について、NC旋盤とマシニングセンタの二台体制から、専用機で一度に加工できるように統合する提案を実施しました。その結果、工程間の搬送や段取りが減り、作業時間は半分以下に短縮されました。専用機の導入には初期投資が必要でしたが、長期的な生産量と投資利益率(ROI)を試算したうえで、投資が回収可能と判断し、実行に踏み切りました。
VA提案の進め方
VA提案を成功させるには、特定の現場だけではなく、企業全体としてスムーズにプロセスを進めるためのステップを踏むことが重要です。以下のステップに従って進行すると、より体系的にVAを取り組めます。
ステップ①情報を集める
まず、対象となる製品や部品、そして工程の現状を正確に把握します。製造コストや品質問題、納期の遅れなど、現在抱えている課題を整理します。加えて、現場での作業手順や不良の発生状況について、定量的なデータ(数値)と定性的なデータ(作業者の声など)をバランスよく収集し、全体像を明らかにしていきます。
ステップ②必要な機能を整理する
製品が果たすべき機能について、その優先順位を明確にすることです。
「この機能は本当に必要なのか」
「より簡単な方法で実現できないか」
といった観点から機能分析を行い、無駄や過剰設計がないかを見直します。また、機能を必須機能と付加機能などに分類し、それぞれのコスト対効果を検討することで、合理的な設計や改善方針を導き出します。
ステップ③コストを調査する
次に、材料費、加工費、設備費などの詳細なコスト内訳を把握し、全体のコストを「見える化」します。まず、どの工程にどれだけのコストがかかっているのかを一つひとつ洗い出し、コストのかかりすぎているポイントを明確にします。さらに、外部委託先の選定や部品の調達先における価格交渉の余地がないかも検討し、コスト削減の可能性を探っていきます。
ステップ④改善案を作成する
材料の変更や設計の見直し、工程の簡略化など、具体的な改善手法を検討するフェーズです。複数の代替案を挙げ、それぞれの費用対効果を定量的に比較・評価します。そのうえで、もっとも効果的かつ実現可能性の高い案を選定します。必要に応じて、実験や試作を実施し、品質への影響や実用性を事前に確認してから本格導入へと進めます。
ステップ⑤一連の流れを振り返り評価する
VA提案によって得られた成果を客観的に測定し、その結果を次の改善活動に活かします。具体的には、コスト削減額や品質向上率、リードタイムの短縮効果などを定量的に計測し、どの程度の効果があったのかを明確にします。また、取り組みの中で発生したトラブルや懸念点があれば、それらに対する対策を早期に講じ、得られた知見を次のプロジェクトにフィードバックすることで、継続的な改善へとつなげていきます。
VA提案の歴史
VAの起源は第二次世界大戦中のアメリカにまでさかのぼると言われています。当時、物資不足が深刻であったため、代替材料や新たな設計を模索する中で「VE(Value Engineering)」の概念が生まれました。 日本では高度経済成長期にトヨタ生産方式の一部としてVE/VAが広がり、1980年代以降、多くの企業がコスト競争力を高めるために導入を進めました。現在では、大手メーカーやサプライヤーだけでなく、中小企業でも活用するケースが増えており、製品開発や工程改善の手法として定着しています。
VA提案に取り組むには会社としての一体感も重要
製造業におけるVA提案は、既存の製品や工程を見直すことで、機能を保ちながらコスト削減を図る有効な手法です。VE提案との違いを理解しながら、素材変更や加工プロセスの改善、設計図面の工夫など、さまざまな側面からアプローチすることで、企業の競争力を大きく高められます。 ただし、VA提案を成功させるには、チームでの連携や現場の声をしっかりと反映させる仕組みが不可欠です。ステップを踏んだ検討と試作・検証を通じて、コストと品質のバランスを保ちながら進めることが重要となります。
このような活動の取り組みをお考えの際には、ぜひファンクショナル・インプルーブメントまでお問い合わせください。












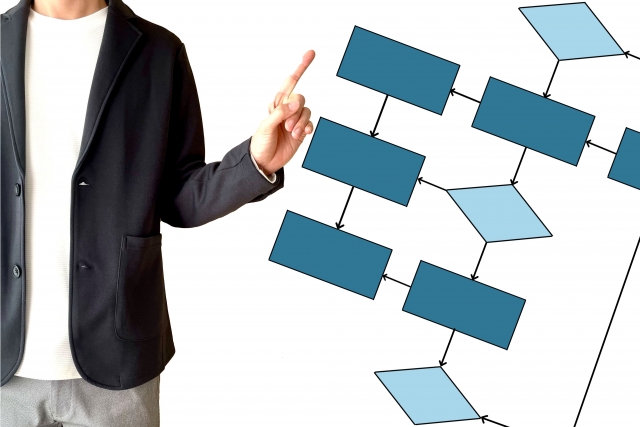
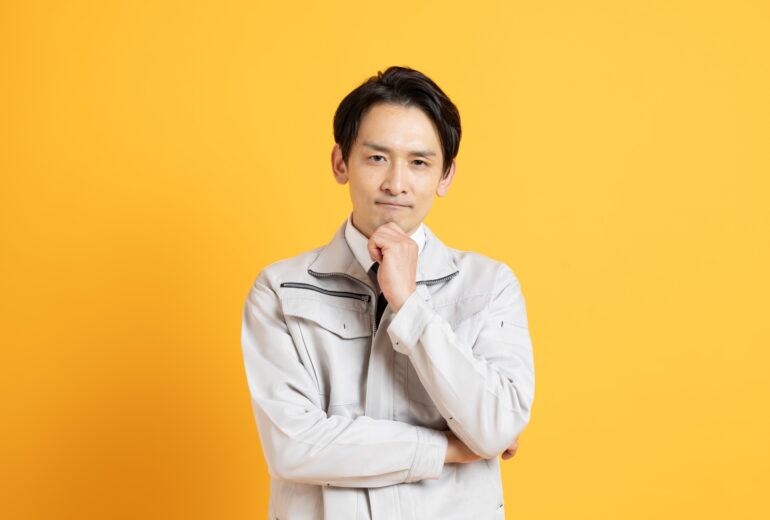


コメント