はじめに
VE(Value Engineering)は「コストを下げる手法」と思われがちですが、本来の目的は価値を上げることにあります。
設計段階でVEを導入することで、コストを削減するだけでなく、使いやすさ・信頼性・デザイン性などの価値要素を高めることができるのです。
本記事では、コストを単に「削る」のではなく、“価値を上げるVE提案”を設計者の視点から実行する方法と実例を紹介します。
VEの定義:価値=機能 ÷ コスト
この式に基づけば、コストを下げるだけでなく、「機能を上げる」ことでも価値は高まります。
設計者が「この機能はユーザーにとって本当に重要か?」と問い直し、新しい提案をすることがVEの本質です。
コストを下げずに“価値”を上げるとは?
- 見た目を改善して“購入意欲”を高める
- 操作性を改善して“ユーザー満足”を高める
- 保守性・交換性を良くして“維持コスト”を下げる
これらは、製品の市場価値や企業の評価に直結する重要な提案領域です。
実例①:カバー構造の一体化で使いやすさアップ
- 旧構造:前面・背面パネルをビスで締結 → 工具が必要で交換に5分
- VE案:スナップ構造+指掛け加工 → 工具レス・30秒交換に
- 結果:コスト変動ゼロ、メンテナンス性は3倍向上 → 顧客満足度アップ
実例②:表示窓の素材変更で視認性アップ
- 従来:グレースモークアクリル
- VE提案:AR(反射防止)PET素材へ変更 → 同価格で視認性2倍
- 結果:機能強化による“誤操作ゼロ”の改善効果を生む
提案の通し方:コストが上がらなくても採用されるVE
- “コストを上げずに機能価値が向上する”ことを明示
- 数字で価値訴求(例:操作時間60%削減、視認性2倍など)
- 営業・カスタマーサポート部門と連携し、顧客視点のメリットを可視化
設計者の役割:VEを“未来の価値提案”と捉える
VEは「削減ありきの評価」ではなく、未来の使われ方を設計に取り込む行為です。
設計者が“使う人”や“売る人”の視点に立ち、構造や機能を再構築することが、単なるコストダウンを超えた“価値創造”になります。
まとめ
設計者が発信するVE提案は、コストを削らずとも顧客満足・生産性・市場競争力の向上に大きく貢献します。
これからのVEは「引き算」だけでなく、「付加価値を加える設計活動」でもあります。
コストではなく、“価値を軸にした改善提案”こそ、設計者がリードするVEの進化形なのです。






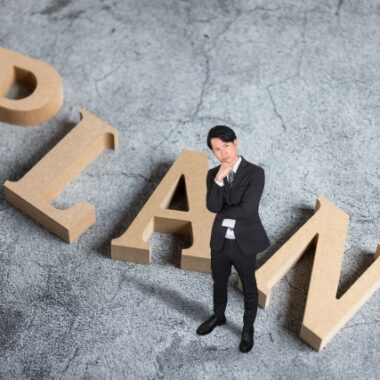








コメント