はじめに
多くの原価問題は、設計完了後に“気づかれる”ことが少なくありません。 「もっと早く言ってくれれば……」という声が、製造・購買・品質現場から上がる背景には、設計初期における情報の分断があります。
設計原価を本質的に下げるためには、“設計者だけで完結しない”体制づくり──すなわち多部門の知見を巻き込んだ初期レビューが不可欠です。
この記事では、その目的・効果・進め方を事例とともに解説します。
設計段階での“独走”が生む問題
- 材質は設計者の好みで決定 → 調達価格が高騰
- 組立しにくい構造 → 製造ラインで時間と不良率が増加
- 加工困難な形状 → 工法変更・再見積もりが必要に
これらはすべて、「早期に相談されていれば防げた」ことがほとんどです。
初期レビューの目的とは?
- 設計段階で“実現性・コスト・生産性・信頼性”を事前に確認
- 各部門の知見を設計に反映する
- 後戻りを防ぎ、量産前の完成度を高める
参加すべき“知見者”とは?
| 部門 | 視点 | 主なアドバイス |
| 製造 | 工法・工数 | 組立性・加工難度・冶具有無 |
| 購買 | 調達性 | 材料・外注費・納期リスク |
| 品質 | 品質保証 | 検査方法・過剰公差・耐久性 |
| 営業・企画 | 顧客要求 | スペックと価格のバランス |
初期レビューの進め方(3ステップ)
- コンセプト設計時点でのレビュー機会を設ける
- 「図面完成後」ではなく「構想設計段階」で共有
- シンプルな情報共有資料を準備
- 材料・構成・主要寸法・目標コスト・用途
- フィードバックを“仕様化”に反映
- 形式だけで終わらせず、設計仕様や方針に反映し議事録化
実例:フレーム構造の初期レビュー
- 設計者案:強度確保のため鋼板溶接構造 → コスト高+加工リードタイム長
- 製造から「曲げ構造でも強度が出せる」と指摘
- 結果:曲げ加工+一体構造で部品点数30%削減、製造時間半減
成功のコツ
- 「設計側が主導」ではなく「全体でつくる」姿勢を持つ
- 評価軸は“コストだけ”ではなく“機能・品質・製造性”を含める
- レビュー結果はテンプレ化して他案件にも展開
まとめ
設計初期に多部門の知見を取り入れることで、手戻りコストや後工程トラブルを未然に防ぐことができます。
“設計=一人で完結する作業”という発想から脱却し、“設計=多部門連携による意思決定プロセス”へ。
それが、設計原価低減の最短ルートです。






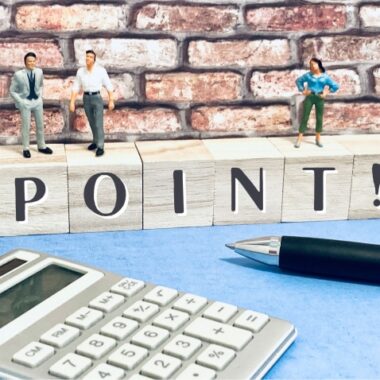









コメント