はじめに
「原価管理はしているが、実際に何が悪いのかわからない」――そんな時に役立つのが「標準原価」と「実際原価」の差異分析です。
本記事では、差異分析の考え方・手順・活用ポイントを具体的に解説します。
定義
• 標準原価:理想的条件を前提にしたコスト計画値(設計図のようなもの)
• 実際原価:実際にかかった費用(実績ベース)
この2つを比較して差が出れば、どこに問題があるかを“定量的に把握”できます。
差異の具体例と原因
差異項目 内容 主な原因 改善の方向
材料費 単価差、歩留差 仕入値変動、不良率 購買戦略、工程改善
労務費 作業時間超過 作業遅延、ミス 作業標準化、教育
間接費 稼働率低下 設備停止、計画ズレ 稼働率管理、保全見直し
差異分析の手順
- 標準原価と実績原価を製品ごとに比較
- 差異が大きい項目を特定
- 差異の要因を“工程・部門・材料別”にブレイクダウン
- 改善対策の立案と実施
実例:差異分析を基にしたコスト改善
• 月次での差異レポートを導入
• 部門別に「最も差異の大きい品目ベスト3」を抽出
• 改善活動のKPIとして差異率を使用 → 翌四半期で粗利改善5%を実現
まとめ
差異は“異常”ではなく“チャンス”です。標準とのギャップにこそ改善の芽があるという視点を持つことで、数字を「使える情報」へと変えていきましょう。
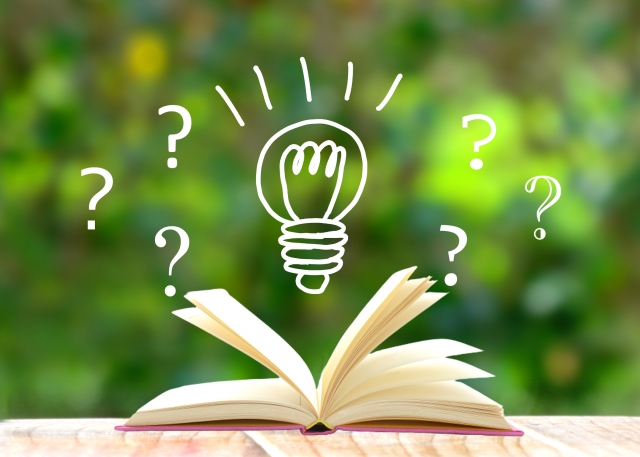











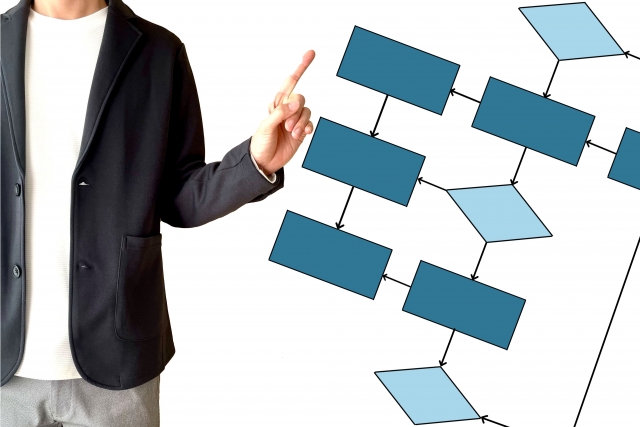



コメント