はじめに
「製造原価の8割は設計段階で決まる」──この言葉は製造業における常識となっています。
しかし、なぜ設計がそこまで大きな影響を与えるのでしょうか?現場でお金が動くのは調達や加工の段階ですが、コストの“中身”は設計段階でほぼ決まっているという事実には、多くの設計者が十分に意識を向けていないのが現状です。
本記事では、その「80%」という根拠と背景、そして設計者が意識すべきポイントについて、実例も交えてわかりやすく解説します。
■ コストは“発生”より前に“決定”されている
コストは、加工や調達によって発生するものですが、「どう発生するか」は設計図によってほとんど決まってしまいます。
例えば、材質・寸法・公差・表面処理といった設計上の仕様が、そのまま材料費・加工費・外注コストを左右するからです。
設計段階での意思決定(例:アルミか鉄か、溶接か一体構造か)によって、実際の金額が変わってくる構造を考えれば、「設計とはコストの青写真を書く行為」であることがわかります。
■ 設計が原価に与える影響とは?
設計段階で決まる代表的なコスト要素:
- 材料費:材質・サイズ・重量(特にコスト影響大)
- 加工費:構造の複雑さ・工法・公差指定
- 組立費:部品点数・組付けの難易度
- 外注費:内作・外注判断・特注品有無
- 物流費:モジュール化・梱包性・輸送効率
つまり、設計図面1枚にコスト構成のほとんどが詰まっているということです。
■ 設計者が押さえるべき3つのコスト視点
- 材料の選定が価格を左右する
同じ機能でも材質を見直すだけで調達コストは数十%変動します。特に樹脂化・アルミ化の検討は重要です。 - 構造が工法と工数を決めている
設計段階で複雑な構造を組むと、加工や組立工数が一気に増加します。加工しやすさや一体成形化などの検討が鍵です。 - 仕様の過剰がコストを引き上げる
±0.01mmの高精度公差や、光沢仕上げなどの“不要なこだわり”は、加工費・検査費・外注費を大きく押し上げます。
■ 実例紹介:部品点数削減によるコスト革新
あるメーカーでは、7部品構成だったカバーを一体構造に変更。
これにより組立工数が45分から15分に短縮され、年間150万円の工賃削減が実現。
さらに在庫点数削減・不良低減・発注業務の簡素化といった副次効果も得られました。
このように、「コストを削る」のではなく「コストの構造を変える」のが、設計段階でのアプローチです。
まとめ
設計段階での意思決定こそが、製造・調達・物流・品質あらゆるコストの出発点です。
設計者が図面を書くという行為は、同時に企業の利益構造を形づくっているとも言えます。 これからの設計は、Q(品質)だけでなくC(コスト)も同時にデザインすることが求められます。
“設計とはコストを描く仕事”である。この認識がVEや原価









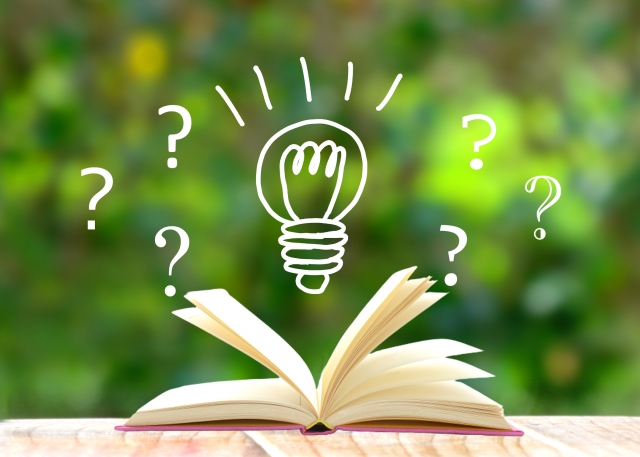





コメント