はじめに
「コストを下げたいが、どこを見直せばいいか分からない」――
そんな悩みに直結するのが、原価構造分析です。
原価構造分析は、単なる費用の一覧ではなく、
「何に、どれだけ、なぜコストがかかっているか」を“見える化”する手法です。
この記事では、以下の3ステップで実践的に解説します:
• 原価明細の分解
• ABC分析による優先度の把握
• グラフ可視化による説得力の強化
- 原価構造を「材料費・加工費・間接費」に分ける
まず、原価を大きく3つに分類して整理します。
分類 内容例
材料費 鉄板、樹脂、電子部品などの購入費
加工費 加工賃、人件費、外注費
間接費 工場光熱費、保全費、間接人件費などの共通費
これにより、コストの“構造”が見えてくるため、分析の出発点として非常に重要です。
- ABC分析で重点項目を洗い出す
ABC分析とは、コスト項目を金額の大きい順に並べ、重点的に対策すべきA群を特定する手法です。
分類 対象割合 代表例
A群 原価の上位20%が占めるコスト 高額部材、大型機械加工など
B群 次の30% 中程度の材料や作業工程など
C群 残り50% 小物部品、消耗品、雑費など
重点的にコストダウンすべきは A群の特定→見直し案の検討 です。
- グラフ化して関係者と共有する
経理データだけでは現場には伝わりません。
原価構造を「グラフ」として見せることで、現場・設計・購買との共通認識が生まれます。
オススメのグラフ形式:
• 円グラフ:構成比のイメージが直感的
• 積み上げ棒グラフ:複数部品の比較に有効
• パレート図:ABC分析との相性抜群
例:材料費が原価の45%、そのうち3品目で80%を占めていた → 材料変更の検討余地あり
実務応用ポイント
• Excelなどで原価明細データを管理している場合、ピボットテーブル+グラフ機能で即可視化が可能
• 設計部門と連携して、「高原価品目が設計変更可能か」を検討
• VE/VAの導入時、構造分析が前提データとして有効
まとめ
• 原価構造分析とは、コストの中身を「材料費・加工費・間接費」に分解して把握すること
• ABC分析を活用し、重点的に削減すべき対象を明確化する
• グラフ化によりチーム全体で認識を共有でき、削減活動の起点になる











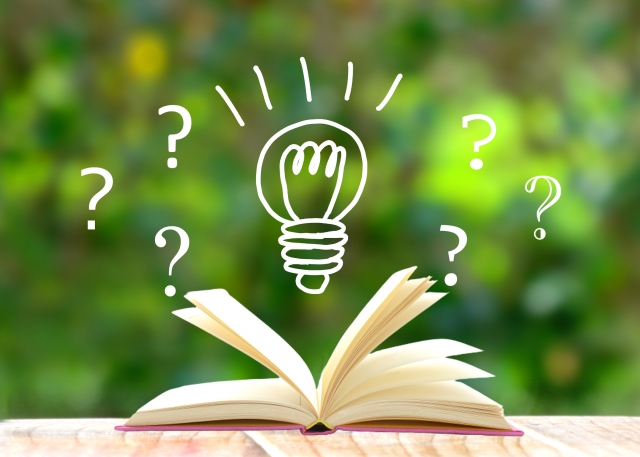




コメント