製造業では、原材料費や人件費など、製品の原価を構成する要素が多岐にわたります。そのため、生産規模が大きいほど小さな無駄が積み重なって莫大なコストにつながり、利益を圧迫するリスクが高まります。
こうした状況を改善するために、多くの企業が生産効率の向上や在庫削減などさまざまなコスト削減策を模索しています。
今回は、製造業の現場で実際に行われたコスト削減の取り組み事例を豊富に紹介するとともに、プロセスの流れや成功のポイント、そして注意すべき点を解説します。自社の状況に合わせて取り組みやすい事例を参考にし、競争力向上と収益改善を実現するための一助としていただければ幸いです。
製造業のコスト削減事例
製造業においてコスト削減を実現するには、製造工程や原材料、人的リソース、固定費など多くの要素を見直す必要があります。それぞれの企業によって重点を置く領域は異なるでしょうが、ここでは代表的な取り組み事例をいくつか取り上げます。
仕入れ先を変更
原材料の調達コストは、製造業における製品原価の大部分を占める場合が多いです。取引先を複数比較検討し、価格交渉やロットの最適化、品質の安定性などを総合的に考慮したうえで仕入れ先を変更することで、大幅なコスト削減に成功した事例があります。例えば、A社は海外の安価な供給元を開拓し、同じ品質を保ちながら原材料費を10%削減しました。品質リスクを避けるために安全在庫を確保しつつ、輸送スケジュールを管理することで納期遅延も防止しています。
こうしたケースでは、安価なだけでなく、品質や物流の安定性、リードタイム、契約条件などを総合的に検討することが不可欠です。また、取引先を変更する際には、旧来の仕入れ先との関係や緊急時のバックアップ体制も考慮する必要があります。安価だが信用度が低いサプライヤーに一極集中すると、いざというときに供給停止リスクが高まるからです。
水道光熱費を節約
工場では、機械の動力や照明、空調などで大量の電力や水資源を消費します。
これらの光熱費を節約するには、以下のような方法が有効です。
- ・節電対策:LED照明や高効率モーターの導入、稼働時間の最適化
- ・節水対策:冷却水や洗浄水の再利用、漏水の点検・修理
- ・自動制御システム:機械のアイドル時間を削減し、必要なときだけ稼働
ある食品加工工場では、洗浄水を循環利用できるシステムを導入し、水道代を年間で20%削減しました。空調機器の運転スケジュールを見直すことで電力使用量を抑え、さらには太陽光発電などの再生可能エネルギーを部分的に導入して電力コストを下げる企業も増えています。
設備管理を徹底
生産ラインの効率を最大化するには、設備の保守点検や故障対応が重要です。故障が起きてから直すのではなく、定期的なメンテナンスと予防保全を行うことで、突発的なトラブルやライン停止による生産ロスを防止できます。大手自動車部品メーカーでは、設備の点検スケジュールをICT化し、部品の交換時期をシステムで管理することで、予測保全を実現してダウンタイムを大幅に削減しました。
長期的にみると、設備更新のタイミングを計画的に進めることもコスト削減につながります。経年劣化した機械をずるずる使い続けるよりも、エネルギー効率の高い新型機器に買い替えることで、メンテナンスコストや光熱費を節約できる場合もあるからです。
機械設備の稼働状況を改善
製造業のコスト削減には、作業効率の向上や機械の稼働率アップも欠かせません。機械が待機状態(アイドリング)で動いていない時間が長いと、無駄な電力消費や作業員の待ち時間が発生します。生産計画を見直し、受注状況に応じた適正な稼働スケジュールを組むことで、ロスを抑えられます。
例えば、同じ工程で複数製品を生産している場合には、段取り替え時間を短縮する方法を検討すると良いでしょう。段取りの標準化やクイックチェンジオーバーの導入により、切り替え時間を大幅に減らし、稼働率を向上させた事例は多く存在します。
新設備の導入を慎重に検討
生産設備を最新のものに更新すれば一時的には生産性が上がるかもしれませんが、多額の初期投資が必要です。投資額を回収するのにどれくらいの期間がかかるか(ROI: Return on Investment)を厳密に試算し、本当に導入すべきかどうかを判断しましょう。導入コストだけでなく、メンテナンス費や操作教育など運用面のコストも含めて考慮することが重要です。
特に、省人化や自動化を目的としたロボットの導入では、導入コストが大きい一方で大幅な人件費削減が期待できる場合があります。生産量が十分に確保でき、長期間稼働する見込みがあれば投資効果が出やすいですが、そうでなければコストを回収しきれない可能性も高いです。
不要な業務や残業を削減
製造現場においては、直接生産に関わらない間接部門やサポート業務が増えがちです。会議や書類作成に時間が取られ、実際の生産活動に集中できないこともしばしばです。RPAやシステム導入などで事務作業を自動化し、従業員がより付加価値の高い業務に集中できるようにするのもコスト削減に繋がります。
また、必要以上の残業は人件費の増加だけでなく従業員の疲労やモチベーション低下を招き、生産性を下げる要因となります。作業工程を再設計し、標準作業時間内で完了できるプロセスを確立することで、残業を削減しつつ効率を高めることが可能です。
活用されていない福利厚生を廃止
大企業を中心に、かつて導入した福利厚生制度がすでに時代や社員のニーズに合わなくなっているケースがあります。使われていない施設やサービスを維持するコストは膨大であることが多いため、実態を調査して活用度の低い項目を縮小・廃止するのも一つの方法です。ただし、社員の士気や定着率に関わる可能性があるため、慎重に判断しなければなりません。
社用スマホの契約プランを見直し
企業によっては、多数の社員が社用スマホを使っている場合があります。通信プランを見直すことで毎月の通信コストを削減できるケースも多く、複数台の回線を一括契約することで割安になる団体プランなども検討します。実際の利用データと料金プランを照らし合わせ、過剰な容量やサービスを利用していないか定期的にチェックするとよいでしょう。
研究開発費を削減
研究開発費は将来の製品競争力に直結するため、単純に削減すれば良いというものではありません。しかし、特に優先度の低い研究テーマや重複する開発ラインなどが存在する場合は、撤退や統合を検討するのも選択肢です。コアとなる技術や戦略的に重要な開発は手厚く投資し、それ以外の部分を削減することで、全体の研究開発費をコントロールできます。
ITツールを導入
在庫管理や生産管理、原価計算といったプロセスをITシステム化すると、データが一元管理され、リアルタイムでの分析や高度な予測が可能になります。クラウド型の生産管理システムやBIツールを活用して、部門間の情報連携をスムーズにし、人的ミスを大幅に減らした事例が増えています。導入費用はかかるものの、長期的にはコスト削減と意思決定の迅速化が見込めます。
製造業のコスト削減の流れ
上記のような手法を具体的に導入するには、システマチックなアプローチが重要です。ここではコスト削減を実施する際の大まかな流れを解説します。
ステップ①削減すべきコストを把握する
まずは現在の費用構造を可視化し、どこに無駄があるのかを把握します。原価計算や損益計算書、内部資料などを活用して、材料費や在庫費、人件費などの各項目ごとの金額と変動要因を洗い出します。部門別、工程別、製品別に集計すると、問題点が浮き彫りになりやすいです。
ステップ②削減のプランを作成する
削減すべき領域を特定したら、具体的な目標とアクションプランを策定します。目標は定量的な指標(例:3か月で在庫コストを10%削減)に落とし込み、達成時期や担当者を明確にします。大きな改善ほど複数部門を巻き込む必要があるため、プロジェクトチームを結成することも多いです。
ステップ③プランを実行する
立案したプランを実際に進めていきます。仕入れ先との交渉や設備の改修、システム導入など、多方面の実務が発生します。既存のオペレーションを変更する場合は、現場や管理部門の理解と協力が不可欠なので、定期的に進捗状況を共有しましょう。
ステップ④結果を分析し、改善を繰り返す
コスト削減施策を実施した結果、どの程度の成果が出たかを評価し、目標との差異を分析します。うまくいった部分はさらに拡大し、効果が見られなかった部分は原因究明して修正を行うことが大切です。PDCAサイクルを回しながら、継続的に最適化を図ります。
コスト削減を目指す際の注意点
コスト削減が経営に有利にはたらくのは事実ですが、やり方を誤ると品質や生産性を損なうリスクもあります。
以下の点に留意して、バランスを見極めましょう。
業務の質や生産性が低下するおそれがある
安易な人員削減や原材料の低品質化は、一時的にコストは下がるかもしれませんが、品質クレームの増加や納期遅延など、長期的に見てデメリットが大きくなる可能性があります。コスト削減の前に、製品の価値や顧客満足度とのバランスを考慮することが必要です。
長期的な視野を持つ必要がある
設備投資や人材育成、R&Dなどはコスト削減と真逆の動きに見えますが、将来的な収益拡大やコスト効率向上をもたらすケースも多いです。目先の数字だけにとらわれず、長期的に競争力を高めるための投資と削減策を両立させる視点が大切です。
優先事項を決めてからコスト削減に取り組もう
製造業におけるコスト削減は、仕入先の見直し、在庫管理の最適化、設備の保守管理の強化など、多角的かつ戦略的なアプローチが求められます。
どの切り口から着手するかによって得られる成果や必要な投資は大きく異なるため、まずは自社の現状を正確に分析し、優先度の高い領域から取り組むことが極めて重要です。
中でも製造原価(特にアッセンブリの場合)のうち、購入部品が全体の約6〜7割を占めることから、仕入先の選定や見直し、部品単価の査定といった調達領域の精緻化は、最も効果的なコスト戦略の一つとなります。
あわせて、競合他社とのベンチマークを通じて市場における自社のポジションを正しく把握することで、競争力の源泉を見極めることにもつながります。
ただし、コスト削減のみを追求した結果、品質低下や将来の成長を妨げるリスクがある点にも注意が必要です。
そのため、短期的な利益確保と長期的な成長戦略のバランスを見極めながら、全社的な視点で意思決定を行う姿勢が求められます。
自社の製造現場や組織全体を巻き込み、コスト構造の見直しと競争力の強化、そして利益率向上を実現するための第一歩として、今こそ具体的な検討を進めてみてはいかがでしょうか。
このような取り組みをご検討の際には、ぜひファンクショナル・インプルーブメントまでお気軽にお問い合わせください。





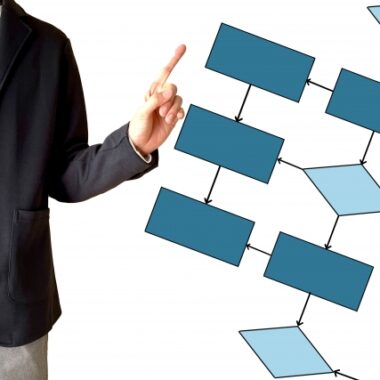





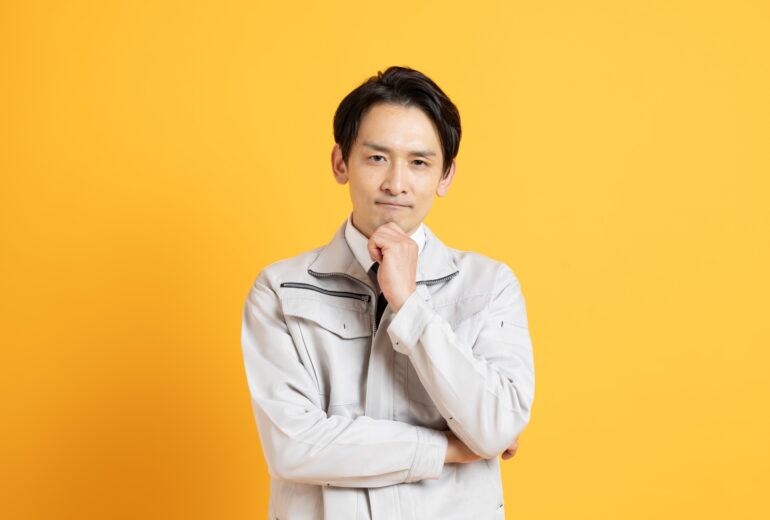



コメント