製造業の経営において、製品をつくるのにどのくらいのコストがかかっているのかを把握する「原価率」は、利益確保や経営戦略を考えるうえで欠かせない指標の一つです。
しかし、原価率が高いほど利幅が縮小し、収益を圧迫してしまいます。
では、理想とする原価率はどの程度なのか、またどうすれば最適化を実現できるのでしょうか。
本記事では、原価率の基本的な考え方や製造業における平均的な水準、そして原価率を抑えるために見直したいポイントを解説します。
コスト削減に課題を抱える企業の担当者は、ぜひ今後の方針策定の参考にしてみてください。
原価率とは
製造業では、製品を作るために投入される材料費や労務費、製造経費といった諸コストの合計を“原価”と呼びます。そして原価率とは、売上に対して原価がどれだけの割合を占めているかを示す指標を指します。
一般的には、次のように算出されます。
原価率=製品の原価/製品の売上×100%
原価率が高ければ高いほど利益が薄くなり、低ければ利益率が高いことを意味します。企業としては原価率を可能な限り抑えつつも品質や納期を確保する必要があり、そのバランスを取ることが経営の重要な課題といえます。
原価率の計算方法
原価率は、売上全体に占める原価の割合を示すため、単純な割り算で導けます。製品が複数ある場合や、製造プロセスが複雑な場合には、製品や工場ごとに細分化して原価を算出し、合計売上に対する比率を計算します。
ロス率とは
ロス率は、材料や工程で生じる廃棄やロスが、どれだけの割合を占めるのかを示す指標です。製造業では、材料の廃棄や不良品による再生産、在庫ロスなどがロス率を押し上げる要因となります。
ロス率の計算方法
ロス率は、例えば次のように算出できます。
ロス率(%)=(ロス数量 ÷ 仕入数量)× 100
製造業における原価率の平均水準
製造業の原価率は業種や製品によって大きく異なります。例えば重工業と食品加工業では、原材料の比率や付加価値の度合いが違うため、適正原価率も異なるでしょう。
ただし一般的には、30~60%程度を目安にするケースが多いといわれています。具体的な数値に関しては、同業他社の決算資料や業界団体のデータ、コンサルティング会社の調査などを参考にするのが良いでしょう。
原価率を抑えるために見直したい項目
原価率が高いと感じたら、まずはコストに大きな影響を与える領域を中心に見直すことが大切です。
以下では、特に重要とされる項目を挙げて解説します。
仕入れ量
材料を過剰に仕入れると、不良在庫や腐敗・劣化のリスクが高まります。計画生産や需要予測の精度を上げることで、必要な分だけ仕入れる仕組みを作りましょう。
仕入れ先
調達コストを抑えるには、仕入れ先との価格交渉や複数のサプライヤーの比較が欠かせません。
ただし安さだけを追求すると品質が低下するリスクもあるため、品質・納期・価格のバランスを考慮しながら選定する必要があります。
仕入れる材料
素材の選択が製品の品質やコストに直結します。高価な素材を使うことで付加価値が高まる場合もあれば、代替素材で十分な機能を発揮できることもあります。
材料選定の見直しは、製品コンセプトや顧客ニーズを踏まえて行うことが重要です。
在庫の管理方法
在庫は資金を寝かせるだけでなく、保管スペースや管理コストも発生します。また、ロスや不良在庫のリスクも高まります。適正在庫を維持するために、需要予測や在庫回転率を管理し、ITシステムの活用も検討すると良いでしょう。
製造工程
製造工程に無駄な作業が多いと、作業時間や材料ロスが増え、原価率が上昇してしまいます。生産ラインのレイアウト変更や作業手順の標準化、機械化や自動化の導入などによって効率化を図ることがポイントです。
注力する商品
自社の中で特に利益率が高い製品や、今後の成長が見込める製品にリソースを集中させることで、全体の原価率を引き下げられる可能性があります。一方ですべての商品を満遍なく生産していては、収益力が伸び悩む恐れもあります。
商品の種類
商品ラインナップが多すぎると、少量多品種の生産となり管理コストが増加します。ある程度の段階で商品を統廃合し、コア製品に集中することで、経営資源を効率的に活用できる可能性があります。
商品の販売価格
原価率を下げるだけでなく、販売価格の見直しを図ることも大切です。値上げにはリスクも伴いますが、ブランド力やサービスを強化することで価格転嫁を可能にし、原価率を抑えつつ利益を確保できるケースもあります。
原価率を理想に近づけるには様々なアプローチが必要
製造業において原価最適化を実現するためには、まず1部品、Assy(アッセンブリ)単位での製造原価の精緻な整備が不可欠となります。
特に材料費においては、原材料の建値や重量を正確に把握し、加工費では労務費・変動費・固定費といったコスト構成要素のレートを明確にすることが求められます。
さらに、販管費についても同様に整備を徹底することで、目標原価との乖離を初期段階で捉え、課題の可視化と早期抽出につなげることが可能となります。
これにより、関係部門を巻き込んだ実効性あるPDCAサイクルを回し、原価管理を企業全体のアクションへと昇華させていきます。
また、レートの把握は企業のコスト競争力を測る重要な指標であり、市場ベンチマークとの比較を通じた自社ポジションの見極めが欠かせません。
原価最適化は単にコストを削減する取り組みにとどまらず、(C:原価低減)と並行して付加価値(F:機能)の高い製品の創出や、販売価格の見直しを通じた利益最大化という視点も重要になります。
加えて、ITシステムを活用した生産管理、需要予測、在庫管理の導入により、部門横断的なデータ共有とコミュニケーションが強化され、原価管理制度の精度が格段に向上します。
このように、企業の競争力を支えるためには、全体最適の視点から原価管理の仕組みを再構築し、継続的な改善を仕掛けていくことが不可欠です。
そのような包括的な原価最適化の取り組みをお考えの際には、ぜひファンクショナル・インプルーブメントまでお問い合わせください。
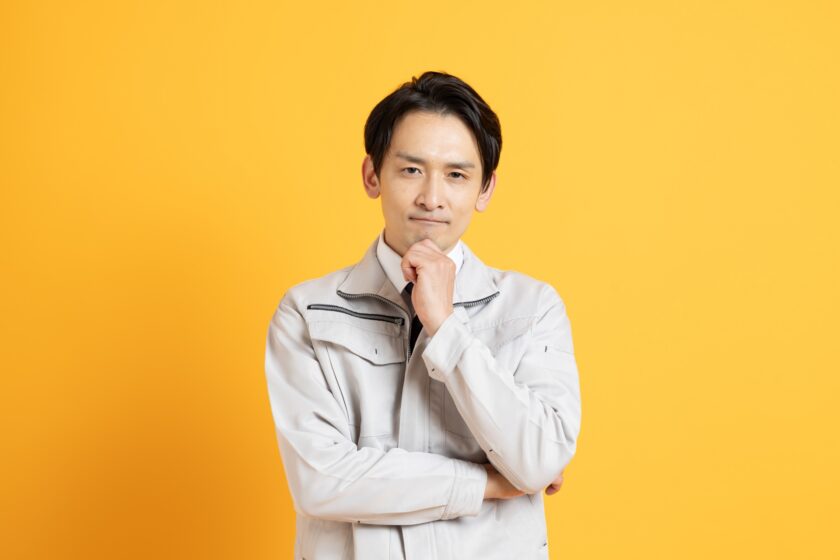







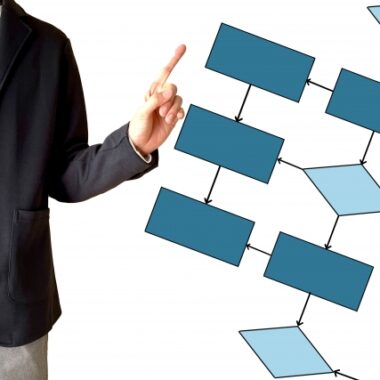







コメント