製造業では、コスト管理が企業の収益や競争力に大きな影響を及ぼします。特に製造原価の高さは、利益率の低下や価格競争での不利につながる可能性があるため、いかに効率良く製造原価を下げるかが大きな課題です。しかし、安易なコストカットは品質や従業員のモチベーションを低下させるリスクも伴います。
本記事では、製造原価の基本や計算方法、平均水準、そして実際に原価を下げるための具体的な方法やポイントを紹介します。従業員の協力や継続的な改善活動など、長期的な視点で取り組むためのヒントを得ていただければ幸いです。
製造原価とは
製造原価とは、製品を製造するために直接かかるコストの総称です。企業が製品を生産する上で必要とされる材料費や労務費、経費などが含まれます。大きく分けると「直接費」と「間接費」に区分されるのが一般的です。
- ・直接費:製品を作るために、直接的に生じる費用を指します。主に、原材料費や直接工賃(現場作業者の給与など)が該当します。1つの製品に対して、どの程度の材料・工数が必要かが明確にわかるものです。
- ・間接費:製品全体にかかる費用を指します。例えば、工場の水道光熱費や管理者の人件費、機械の減価償却費などが含まれます。個々の製品に直接割り当てるのが難しいコストを「間接費」としてまとめているのが特徴です。
製造原価を適切に把握するには、直接費と間接費の振り分けを正しく行うことが重要です。間接費が大きくなりがちな業態では、間接費の管理や配賦の精度を高めることで、原価低減のヒントを得ることができます。
製造原価の計算方法
製造原価を正確に算出することは、適切な原価管理や価格設定を行うための基礎となります。
一般的には、以下のような算式が用いられます。
製造原価=(総製造費用+期首の材料費+仕掛品の棚卸高)−(期末の仕掛品+未使用材料費)
- ・総製造費用:材料費(直接費)+労務費(作業者の人件費)+経費(間接費)を合わせたもの
- ・期首の材料費 / 期末の仕掛品 / 未使用材料費:決算期や月次で締める際に在庫として計上される金額
この計算により、一定期間における実質的な製造原価が把握できます。仕掛品や材料在庫の増減が大きい企業では、在庫管理と合わせて計算の整合性を取りながら行うことが重要です。
製造原価の平均水準
業種や生産形態によって大きく異なりますが、製造原価の全体に占める「直接材料費」「直接労務費」「間接費」などの比率を把握することで、コスト構造を可視化しやすくなります。
例えば、原材料の割合が高い企業では素材価格の変動に敏感になりやすく、人件費の割合が高い企業では労働生産性の向上や働き方改革が課題になりやすいでしょう。
一概に「平均水準」を論じることは難しいものの、参考として製造原価率(売上に占める製造原価の割合)が50〜70%程度に落ち着く企業が多いとされています。
ただし、これは製品やサービスの付加価値、経営戦略によって大きく変わります。
製造原価を下げる方法
製造原価の低減は、企業の利益率向上や競争力強化に直結します。ただし、無理なコストカットは品質低下や従業員モチベーションの低下を招きかねません。
以下では、バランスを保ちつつ原価を下げるための代表的な方法を紹介します。
固定費を抑える
固定費には家賃やリース代、減価償却費、管理部門の人件費などが含まれます。これらは生産量にかかわらず発生する費用です。固定費を見直すことで、原価構造の改善が期待できます。
下記のような取り組みが選択肢として考えられます。
- ・設備投資の精査:新規設備導入時にROI(投資利益率)を検討し、不要な設備を導入しない
- ・リースやサブスク契約の見直し:使っていないサービスや設備契約がないか確認する
業務効率の良い仕組みをつくる
生産プロセスを見直し、ムダな工程や重複作業を排除することで、作業時間や人件費を削減できます。
具体的には、以下のような取り組みが考えられます。
- ・ライン生産やセル生産の導入:流れ作業を整理し、効率的に作業が進むようレイアウトを最適化
- ・在庫管理システムの導入:過剰在庫や欠品を防ぎ、資金効率を高める
LED照明に切り替える
工場や倉庫の照明をLED化することで電力使用量を削減し、光熱費を下げることができます。
長寿命なLEDを導入することでメンテナンスコスト(交換作業や資材費)も節約可能です。
節水弁を取りつける
生産プロセスにおいて大量の水を使用する業態の場合、トイレや手洗い場などに節水弁を設置することで水道料金を抑えられます。
わずかな削減でも長期的に見ると大きなコスト削減につながることが多いです。
地下水を利用する
地域や設備環境によっては、地下水をポンプで汲み上げて使用する方法があります。使用量によっては水道料金の削減につながりますが、導入に際しては設備投資や法規制の確認が必要です。
ネット回線や社用携帯の契約プランを見直す
通信費や電話料金も積もり積もれば大きな固定費となります。企業規模が大きいほど従業員数に比例して費用が膨らむため、
一斉に契約プランを見直すことで大幅な削減が見込める可能性があります。
IT技術を導入する
生産管理システム(MES)やERP、クラウドサービスなどを活用して、在庫管理や受発注、原価計算を自動化・可視化すると、ヒューマンエラーや二重入力などのムダを減らせます。
データ分析によって生産効率のボトルネックを特定し、改善策を導き出すことも可能です。
製造原価を下げるポイント
原価低減を成功させるには、具体的な方法論だけでなく、企業全体の意識や継続的な改善活動が不可欠です。
以下のポイントを押さえながら取り組むことで、より効果的な原価削減につなげられます。
従業員全員の協力を得る
原価を下げるための活動は経営層や管理部門だけでなく、現場スタッフや全社的な意識共有が重要です。定期的なミーティングやアイデア募集を行い、小さなムダを拾い上げることで、組織全体でコスト意識を高められます。
成果を共有するとモチベーション向上にもつながるでしょう。
5S活動で職場環境を整える
5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)活動は、職場環境を見直し無駄を排除する基本的なアプローチです。道具の配置や在庫の置き場などを明確にすることで、探す時間や紛失リスクを減らし、結果的にコスト削減や生産性向上に寄与します。
原価低減活動は継続的に行う
原価削減は一度きりの取り組みではなく、日常的・継続的に改善を重ねることで大きな成果を得られます。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回し、定期的に見直しとアップデートを行い、常に最新のコスト構造を把握しておくことが大切です。
製造原価の低減は組織的・長期的に取り組むことが重要
「原価低減は、企業の利益力と製品の競争力を左右するカギです。」
製造原価は主に「材料費」と「加工費」に分かれますが、特に材料費は全体の6〜7割を占めるため、ここにメスを入れることが大きな効果を生み出します。
そのためには、材料の機能や要求を見直し、「本当に必要か?」を問い直すことが重要です。これにより、本来の機能、要求に立ち返り、着実なコストダウンが実現できます。
さらに、原価低減は一度きりの取り組みではなく、社内全体で継続的に進めるべき“文化”です。
日々の5S活動や小さな改善も、積み重ねることで大きな成果につながります。
原価低減は単なるコストカットではありません。継続的な改善の訓練を通じて、成果が“見える化”され、品質向上や従業員のモチベーション向上にもつながる、企業全体の成長エンジンなのです。
是非この改善にご興味あればファンクショナル・インプルーブメントにお問い合わせください。





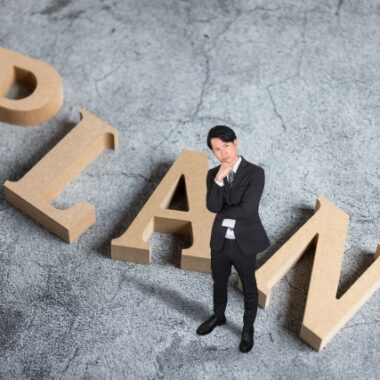



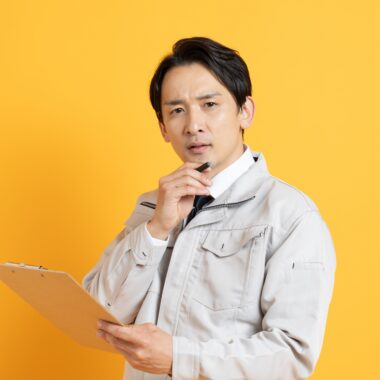






コメント