製造業では、原材料費や労務費、製造に必要なさまざまな経費が積み重なり、最終的な製品価格に大きな影響を与えます。これらのコストを適切に把握し、最小限に抑えつつ利益を確保する「原価管理」は、企業の競争力を左右する重要な業務です。
しかし、実際には正確なコスト情報をリアルタイムで収集できなかったり、部門間の意思疎通が不十分だったりと、課題が多いのも事実です。
本記事では、原価管理の基礎から、製造業における原価管理の課題、さらには解決策の糸口となる管理の流れや他社との競争力を高めるコツなどを詳しく解説します。
原価管理とは
原価管理とは、製品やサービスを生み出すためにかかるコストを正確に把握・分析し、継続的に改善していくプロセスのことを指します。特に製造業では、原材料費や人件費、設備投資など多岐にわたる費用が発生し、かつ生産プロセスが複雑であるため、原価管理が企業の収益性や競争力に直結します。
原価管理が不十分だと、どの工程でコストが増大しているのか、製品の利益がどの程度確保されているのかが把握しづらくなり、結果として採算の取れない製品を作り続けたり、適切な価格設定ができなかったりといった問題を引き起こす可能性があります。
原価の種類
原価と一口に言っても、その測定方法や対象によっていくつかの分類があります。
ここでは代表的な原価を2つの視点から紹介します。
製造原価
製造業においては、主に「材料費」「労務費」「経費」の3つを合算して製造原価を算出します。それぞれの内訳は以下の通りです。
- ・材料費:原材料や補助材料など、製品の製造に直接必要な材料のコスト
- ・労務費:作業員の給与や手当、福利厚生費用など人件費に該当するもの
- ・経費:機械の減価償却費や光熱費、修繕費など、製造に間接的に関わる費用
これらを総合して「製造原価」とし、製品単位、ロット単位、工程単位など、さまざまな単位で把握していきます。
標準原価・見積原価・実際減価
原価を計算するタイミングによって、以下の3種類に分かれます。
- ・標準原価:あらかじめ設定した「理想的な条件下での原価」。生産効率や材料費のロスを最小限にした時のコストを想定しているため、コスト管理の目標値として活用される
- ・見積原価:受注前に見積もりを行う際に算出する原価。受注獲得や価格交渉の参考にされる
- ・実際原価:実際に生じた費用を集計した原価。生産終了後、実績に基づいて計算する
標準原価や見積原価と実際原価の差を分析することで、どの工程で無駄が生じたのかなど、改善点を把握しやすくなります。
製造業における原価管理の課題
原価管理は企業の利益確保やコスト削減に不可欠な施策ですが、実際の運用段階でいくつかの課題に直面するケースが多いです。
以下では代表的な課題を挙げます。
正しい原価をリアルタイムで把握できない
生産現場の数値を手作業で集計している場合や、システムが整備されていない場合、正しい原価が即座にわからないまま生産が続行されることがあります。
これにより、採算割れや不良品の大量生産に気付くのが遅れ、損失が拡大する恐れがあります。
従業員のスキルが不足している
原価管理の手法やシステムの活用、データの分析には一定の知識と経験が必要です。スキルが不足していると、分析が形骸化してしまったり、改善アイデアを引き出せなかったりして、せっかくの情報が活かされないことがあります。
原価を適切に配分するのが難しい
複数の製品を同じラインで製造している場合、共通で使用する材料や設備のコストを製品ごとにどう配分するかが難しいです。配分方法を誤ると、本当に利益が出ている製品とそうでない製品の判別ができなくなります。
部門間のコミュニケーションが不足している
製造部門、営業部門、財務部門などがそれぞれ独立して情報を管理していると、全社的な原価の最適化が進まないケースがあります。
システムや会議体制を整え、情報共有と改善提案がスムーズに行える環境を作ることが大切です。
原価管理の流れ
原価管理を効果的に行うには、一連のプロセスを体系的に進める必要があります。
以下では、代表的なフローを4ステップで紹介します。
①標準価格と標準原価を定める
まずは、理想の生産条件を想定し、1個あたり、または1ロットあたりでどの程度コストがかかるかを標準原価として設定します。これが日常的な原価管理やコスト分析のベースラインになります。
②実際のコストを把握する
生産活動が始まった後は、材料費や人件費など、各種コストをリアルタイムで収集・記録します。工場内のシステムやIoT技術などを活用すると、手作業による記入ミスや集計の遅れを防げます。
③目標と実際の差を分析する
標準原価と実際原価の差(差異)を見て、どの部分で想定よりコストがかかっているのかを明確にします。
材料費の高騰や作業時間の延長、設備のトラブルなど、差異の原因を深堀りしていくことが重要です。
④改善策を考えて実行する
差異の分析結果に基づき、コスト削減の具体的な施策を立案します。例えば、工程レイアウトを見直す、購入先を変更する、作業手順を標準化するなど。実行後も継続的にモニタリングと改善を繰り返すことで、原価管理の精度が高まります。
原価管理で他社と差をつけるために必要なこと
原価管理は、コスト削減だけが目的ではなく、企業全体の戦略や収益性に大きく関わってきます。そこで、他社よりも一歩先んじるために意識したいポイントを紹介します。
収益性の向上
原価を下げるだけでなく、適正な価格設定や付加価値の創造によって、収益性を高めるアプローチが重要です。顧客が求める価値に合った製品を提供し、同時にコストを削減することで、利益率をアップさせられます。
無駄なコストの削減
工程ロスや在庫ロス、不要な工程など、いわゆる“ムダ”を徹底的に洗い出すことが原価管理の基本です。リーン生産方式などを導入する企業も増えており、プロセスの見直しや自動化が効果を上げています。
意思決定の迅速化
正確な原価情報がリアルタイムで共有されれば、現場レベルから経営層まで迅速な意思決定が可能になります。特に製品の仕様変更や新規受注対応など、スピードが勝敗を分けるビジネスシーンで原価管理の整備が効果を発揮します。
競争力の強化
コストを最適化しつつ品質を維持・向上できる企業は、市場での競争力を大きく高められます。原価管理をベースにした経営が浸透することで、日々のオペレーションから新規プロジェクトに至るまで、全社的なコスト意識が高まり、優位性を築けます。
原価管理が企業の継続的な成長可否を左右する
製造業における原価管理は、単にコストを削減するだけでなく、製品の品質や企業の収益性、さらには市場での競争力を左右する重要な経営課題です。標準原価・見積原価・実際原価などの違いを正しく理解し、リアルタイムで正確なコストを把握する仕組みを整えることが大切です。また、製造現場だけでなく、営業や財務、企画など各部門が連携しながら、改善策を具体化・実行することが欠かせません。
原価管理を効率よく進めるには、ITツールや生産管理システムの活用、従業員のスキルアップ、定期的な見直しのサイクルなど多方面での取り組みが必要です。適切な原価管理を行うことで、商品力や企業ブランドの信頼を高め、長期的な安定と成長を手に入れる為に、是非ファンクショナル・インプルーブメントにお問い合わせください。
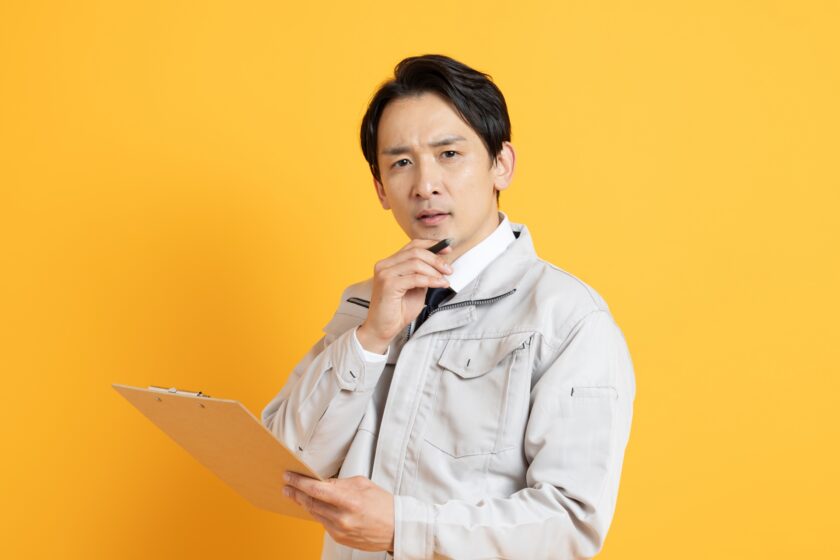















コメント