製造業では適正な価格設定や利益率向上のために、原価を正しく把握し管理することが欠かせません。なかでも「原価計算」は、材料費や労務費、経費などのコストを洗い出し、それぞれが製品のどの部分にどの程度かかっているかを明確にするための手法です。しかし、原価計算と一口にいっても「標準原価計算」「実際原価計算」「直接原価計算」など複数の方法があり、企業の状況や目的に応じた選択が必要となります。
本記事では、原価計算の基本的な概念や計算手順、さらには原価率を改善するためのポイントを詳しく解説します。原価計算を導入・見直しする際の参考情報として、ぜひ活用してみてください。
原価計算とは
原価計算とは、製品やサービスを提供するためにかかった費用を把握し、その結果を経営に活かすための仕組みです。製造業においては、製品1個あたりのコストや部門別コストを正確に把握することで、原価低減や価格戦略の策定に大きく貢献します。
原価計算の目的
原価計算をする主な目的は以下のとおりです。
- ・コスト把握と価格設定:製品ごとの実際のコストを明確にし、適正な販売価格を設定できる
- ・経営判断の指標:利益率の高い製品や改善が必要な工程などを判断するためのデータとして機能
- ・在庫評価:原価がわかることで棚卸資産(在庫)の評価を適切に行い、財務諸表に反映できる
製造原価とは
製造業が製品を作る際にかかる費用を総称して「製造原価」と呼びます。
具体的には、「材料費」「労務費」「経費」の3つに分けて考えることが多いです。
材料費
製品の主原料や副資材など、直接製品に組み込まれる費用を指します。
材料費は外注仕入れ分も含め、在庫管理や購買コストの最適化などが原価低減につながる重要な要素です。
労務費
工場での作業員の給与や残業代、社会保険料などが含まれます。特に直接工の労務費は、作業時間の管理や生産性向上がコスト削減のカギとなるため、勤怠システム導入や工程分析などの方法で最適化を目指すことが重要です。
経費
光熱費や通信費、設備の減価償却費など、製造に必要な間接的なコストを指します。このうち直接製造に関係していない費用は間接費として扱われる場合もあるため、経費と間接費の切り分けを明確に行うことが大切です。
直接費と間接費
原価をより正確に把握するには、費用を「直接費」と「間接費」に分類する方法が有効です。
- ・直接費:製品1個あたりに直接的に紐づけられる費用(例:特定製品のために使用する材料費や作業工賃)
- ・間接費:製品単位では割り当てが難しい費用(例:工場全体の光熱費、事務所の家賃、管理者の人件費)
多品種少量生産が主流の製造業では、間接費が大きくなりがちで、製品ごとにどう配賦するかが原価計算のポイントとなります。
原価計算の種類
原価計算には大きく分けて「標準原価計算」「実際原価計算」「直接原価計算」の3種類があります。それぞれの特徴と使い分け方を理解することで、自社の生産形態や経営戦略に合った方法を選択できます。
標準原価計算
標準原価計算は、あらかじめ標準的な材料費や労務費、経費などを設定し、その基準と実際にかかったコストを比較して差異を分析する手法です。差異分析がしやすく、コスト管理や業務改善のための指標として活用しやすいというメリットがあります。一方で、設定した標準値が実態とずれていると、差異が大きくなりすぎて正確な分析ができず、かえって意味をなさなくなるというデメリットもあります。
実際原価計算
実際原価計算は、実際に発生した材料費や労務費、経費などを製品ごとに正確に配賦して原価を算出する方法です。現場での実際のコストを反映しやすいため、精度の高い原価管理が可能になるというメリットがあります。しかしその一方で、計算や配賦が複雑になりやすく、集計や管理にかかる作業コストが高くなるというデメリットもあります。
直接原価計算
直接原価計算は、変動費(主に材料費や一部の労務費など)だけを製品コストとして計算し、固定費は期間費用として処理する手法です。この方法は、損益分岐点分析などを通じて利益構造を簡単に把握しやすいというメリットがあります。ただし、すべてのコストを製品に割り当てないため、外部報告を目的とした財務会計には適していないというデメリットがあります。
原価計算の方法
それぞれの原価計算の種類に応じて、計算の手順やデータの扱い方が異なります。ここでは「標準原価計算」「実際原価計算」「直接原価計算」の場合の進め方の概要をまとめます。
標準原価計算の場合
標準原価計算の場合、以下のステップを踏みます。
- 1.標準コストを設定:作業手順や材料単価、工数などを分析して、標準的な1製品あたりの原価を見積もる
- 2.実際コストとの比較:生産実績を集計し、材料費や工数などの実際コストと照合する
- 3.差異分析:差異がどこから生じたのか(材料価格差異、工数差異、歩留まり差異など)を特定し、対策を立案
実際原価計算の場合
実際原価計算は以下のステップで行います。
- ・製品ごとの直接費を集計:材料費や直接工賃など、製品に直接紐づくコストを計上
- ・間接費の配賦:工場全体の光熱費などを適切な配賦基準(工数、機械稼働時間など)に基づいて製品に割り当て
- ・合計原価の算出:各製品の直接費と割り当て間接費を合計し、製品原価を確定する
直接原価計算の場合
直接原価計算を行う場合は下記のステップで行います。
- 1.製品ごとの直接費を集計:材料費や直接工賃など、製品に直接紐づくコストを計上
- 2.間接費の配賦:工場全体の光熱費などを適切な配賦基準(工数、機械稼働時間など)に基づいて製品に割り当て
- 3.合計原価の算出:各製品の直接費と割り当て間接費を合計し、製品原価を確定する
原価計算を行う2つの方法
原価計算を実施する際、企業の規模やシステム導入状況などに応じて、「人の手による計算」と「原価管理システムの利用」の2つの方法が選択肢となります。
人の手で計算する
手動で計算を行う場合、システム導入にかかるコストがほとんどなく、自社の業務に合わせて柔軟にカスタマイズできるというメリットがあります。一方で、人為的なミスが起こりやすく、扱うデータ量が増えると作業負荷が大きくなるというデメリットもあります。
原価管理システムを利用する
原価管理システムを利用する方法では、生産管理ソフトやERPシステムなどと連携し、原価計算を自動的に行うのが特徴です。作業効率が高く、リアルタイムで原価を把握できるため、迅速な経営判断にもつなげやすいというメリットがあります。一方で、システムの導入や運用にはコストがかかるほか、適切なシステムの選定や、使いこなすための知識・スキルが求められるというデメリットもあります。
原価率を改善する方法
原価計算によって問題点を把握したら、次は実際に原価率を下げる取り組みを検討します。以下の2つのアプローチは、多くの製造業で導入・検討される方法です。
材料費を抑える
材料費を抑えるためには、以下のような取り組みが推奨されます。
- ・サプライヤーの見直し:同じ品質の資材をより安価に提供するサプライヤーを探す
- ・共同購入・一括購買:複数の事業所や部署で一括して資材を購入し、スケールメリットを活かす
- ・歩留まりの向上:加工ロスやスクラップを減らし、使用材料を最適化する
製造工程の無駄を省く
製造過程の無駄を省くためには、以下の取組を行います。
- ・工程分析:作業の流れを可視化し、無駄な動線や待機時間を減らす
- ・人員配置の最適化:作業負荷の偏りを是正し、労働効率を向上させる
- ・機械稼働率の向上:ダウンタイム(故障・メンテナンスなど)を減らし、生産量を安定化させる
製造業における原価計算は企業の経営戦略に不可欠
原価は製品の図面が確定した段階で約80%が決まるため、原価計算は開発の初期段階から行うことが極めて重要となります。
その段階で設計・調達・生産技術の知見を融合させ、製品に求められる機能や特性を基に最適な材料選定を行うことが、将来的なコスト競争力を大きく左右します。
特に材料費は原価構成の中で約6〜7割を占めるため、ここに焦点を当てた取り組みが原価低減に直結します。
加えて、コスト上昇を抑えるためには特殊材料の使用を極力避け、汎用材料を優先的に選定する姿勢が求められます。
同時に、製造工程の選定とその効率化も見逃せない要素であり、無駄を省きながら品質を確保するための工夫が必要です。
これらの活動をさらに効果的に進めるには、ITシステムの導入によって設計段階から多角的な検討を可能とし、定量的な判断とスピード感のある改善を両立させることが有効です。
こうした一連の取り組みは、企業の競争力を高め、利益率の向上や持続的な成長へとつながる強固な基盤となります。
原価管理を単なるコストの把握ではなく、経営戦略の一環として総合的に実践していくことが、これからの企業に求められる姿勢です。
そのような取り組みを検討される際には、ぜひファンクショナル・インプルーブメントまでお問い合わせください。










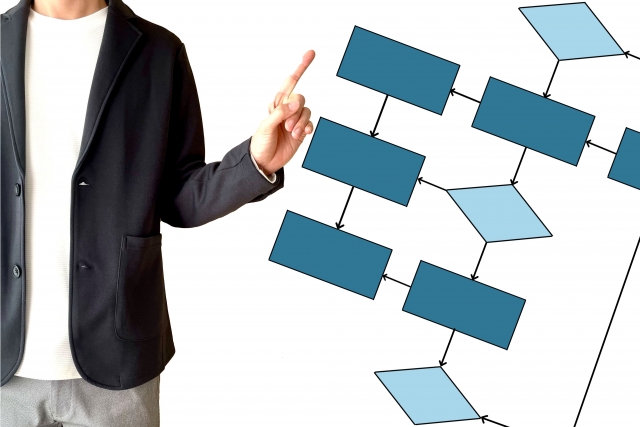





コメント